
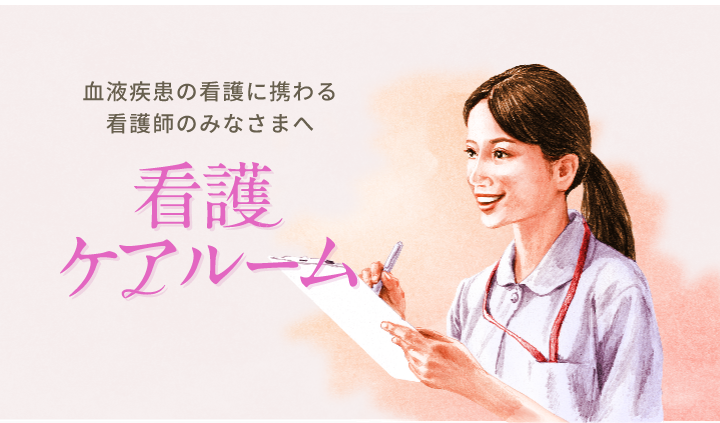

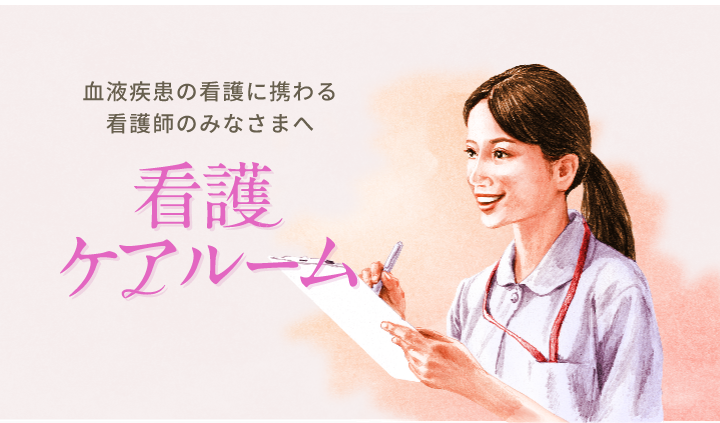
検査・診断、治療や移植にかかわる
看護ケアのポイントや
患者さまの心のケアについて説明していきます。
先生からのメッセージは
現場の生のアドバイスをいただいています。
抗がん薬の血管外漏出は皮膚障害を起こし、漏出の範囲、薬剤の種類や量によっては、皮膚組織の壊死な
どの深刻な障害を引き起こすため注意が必要です。
しかし、十分に注意をしていてもさまざまな要因で発生する可能性があり、
かつ治療法も確立されていないので、早期発見・早期対応が重要となります。
障害の程度は薬剤の種類によって異なるので、薬剤の把握と患者さんのセルフモニタリングによる
早期発見を促すアセスメントとケアが求められます。
血管外漏出とは、点滴で血管内に投与されるべき薬剤が血管外に漏出することにより、周辺組織に障害を生じることをいいます。症状には、発赤、腫脹、疼痛、灼熱感などがあり、症状が進むと水泡が形成されたり潰瘍ができたりします。そして、まれに壊死する場合もあります。
抗がん薬の種類によってリスクは異なり、障害の程度の強い順に、起壊死性抗がん剤、炎症性抗がん剤、非壊死性抗がん剤に分けられます。起壊死性抗がん剤は組織障害のリスクが高く、少量の漏出でも障害を発生させ、皮膚組織にとどまらず、漏出周囲の腱や神経にも影響を及ぼします。運動障害、感覚障害を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です1)。
また、一度、血管外漏出を起こした患者さんでは、後日に別の血管から抗がん薬治療を行う際に、過去に血管外漏出を起こした部位に皮膚障害が生じることがあります2)。これをリコールアクションといいます。
表 血管外漏出時の組織障害性による分類
血管外漏出は、抗がん薬の種類によってリスクが異なるため、 リスクに応じた予防、早期発見・早期対応が大切です。
早期発見のためには、抗がん薬の投与前からリスク因子をアセスメントし、定期的なモニタリングを行ないます。モニタリングは、刺入部に発赤、腫脹、疼痛などを含めた違和感がないか、点滴速度の低下や静脈血の逆流がないかを確認します。抗がん薬の投与時には血液の逆流の確認、持続投与時は1時間ごとに血液の逆流の確認を行う必要があります3)。
血管外漏出を確実に予防することは困難なため、発生時にすぐに対処できるように、対処の流れを把握しておくことが重要です。
漏出が疑われた場合は、ただちに抗がん薬の投与を中止し、医師に報告します。留置針はすぐに抜かずに、注射器で血液を3~5mL吸引後、陰圧を保ちながら、抜針し、漏出部位を油性ペンでマーキングします。 次に抗がん薬の種類に応じた対処を行います。
起壊死性抗がん剤
ステロイド薬の局注、ステロイド外用薬の塗布を行い、薬剤の特徴に合わせて冷却もしくは加温(保温)を行います。治療薬が使われることもあります。
血管外漏出の早期発見・早期対処には、患者さんから些細なことでも変化を感じたら訴えていただくことが重要です。よって患者さんに具体的な症状やセルフモニタリングの必要性を予め理解してもらうことが大切です。
具体的には、点滴部位の疼痛、腫脹、灼熱感、それ以外の違和感、点滴の滴下速度の低下などがあります。「チクチクする」「ジーンと熱く感じる」「ビリビリする」などの症状、あるいはそれ以外の違和感があっても、「たいしたことはない」と放置せず、すぐに看護師に報告するように伝えます。患者さんは、「これくらいで看護師さんを呼んでいいか迷った」などと、違和感があっても遠慮して言わないこともあるので、わずかな症状や変化でも報告してもらう環境をつくることが大切です2)。
また、自宅へ帰った後に症状が出現することもあるので、点滴をした部位に変化が見られたときは、すぐに病院へ連絡するように伝えることも大切です。
資料
1) 野島陽子. 看護技術 2021;67(13):1371-1380.
2) 淺野耕太. YORi-SOUがんナーシング 2020;10(6):20-24.
3) 中内香奈. がん看護 2020;25(2):116-120.
4) 谷村紀代子ほか. 消化器ナーシング 2021;26(9):838-843.

